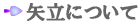ホーム Home >矢立について The yatate
 |
 |
|
| 矢立は、われらの父祖が愛用した携帯用筆記具である。昔、武士が戦場で矢を立てて背に負った箙の下の小袖出しに入れておいた硯を、「矢立の硯」といったが、その筆記具が携帯に便利なように改良された後も、これをつづめて「矢立」と呼び慣わすようになった。 矢立の始まりは鎌倉時代という。初期の矢立は檜扇型で、上部の蓋を横にずらすと筆と墨壺が納められていた。墨壺には、もぐさや綿のようなものを入れて墨汁を浸み込ませてあり、墨汁が乾燥すると水を滴らせて使ったのである。 鎌倉時代に画かれた絵巻物「蒙古襲来絵詞」(1293年)の「李長分捕の首実検」の場には、檜扇型の矢立を使っている場面が描かれている。 江戸時代に入り、芭蕉の「奥の細道」の冒頭「行く春や鳥啼き魚の目は泪 これを矢立の初めとして 行く道なお進まず」のくだりは有名である。芭蕉が「奥の細道」に携帯した矢立は、桑製檜扇型で、門人小沢ト天が特別に誂え、旅立ちのはなむけとしたものといわれる。 芭蕉は檜扇型の矢立を使用したということであるが、江戸時代には、墨壺を大きくし、これに筆筒を直結して柄杓型とし、腰帯に差して携帯するのに便利なものが一般的となる。文献には、寛政の頃(1789〜1801年)に一時、墨壺と筆筒の分離した印籠矢立(分離型)が流行するが、やがてそれがすたれて再び一体型が主流となったとある。この頃、庄屋には俵差のついた矢立、職人には物差のついた矢立、商人には算盤や秤に仕込んだ矢立、女性には簪に仕込んだ矢立、文武両道用には短銃矢立など、様々な創意工夫のこらされた機能性の高い矢立が生まれた。 さらに幕末には方形を基本とする箱型の懐中矢立も出廻るようになる。箱型矢立の筆は、振出式、捻子継式等短くする工夫をして箱の中に収納されている。このように矢立の形は、扇型、一体型、分離型、箱型を基本とし、これから脇差型、机上型など様々な変型が開花していくのである。 とくに幕末から明治の初めにかけては、外人の収集を意識したのか、目先の変った変型矢立が多く作られている。 刀、鉄砲、笛太鼓、三味線、千両箱など様々な形がある。矢立の素材は、銀、真鍮、白銅、鉄など金属が多いが、象牙、鼈甲、瓢箪、茸、藤、竹、陶磁器等多種である。 明治になり、万年筆が輸入され、普及するようになると矢立も漸次その姿を消していった。 当館に展示された矢立の一つ一つを、いつ、どのような人が、どんな場面でこれを使ったのであろうかと、その想いを遡らせるとき、矢立鑑賞の興はつきることがない。 公益財団法人 俵美術館
初代理事長 俵 正市 |
||
 |
 |